日本経済新聞:2001(平成13)年10月25日
妊娠中たばこ多いと‥‥
出生児の身長・体重低下
妊婦の喫煙率>>10%に増加
妊娠中の母親の喫煙本数が多いほど、出生時の赤ちゃんの体重や身長が低下する傾向にあることが、厚生労働省が24日発表した「2000年乳幼児身体発育調査」で分かった。妊婦の喫煙率は一割に達し、特に10代では、3割を越えていた。全体として出生時の赤ちゃんのスマート化は続いているものの、同省は「たばこが出産に与える影響がかなり明らかになった。注意喚起していきたい」としている。
調査は1950年以来、10年ごとに実施。2000年の調査では小学校入学前までの乳幼児のうち全国から抽出した1万21人と、2000年9月中に病院で生後1カ月健診を受けた4094人の計1万4千115人の出生時の状況をまとめた。
全体では、出生時の平均体重は男児が3.04㌔(10年前の前回比110㌘減)、女児は2.96㌔(同100㌘減)。平均身長は男児が49.0㌢(同6㍉減)、女児が48.4㌢(同5㍉減)で、体重は男女とも80年、身長は男児が70年、女児が60年の調査をピークに減少を続ける傾向は変わらなかった。
同省は「妊娠中毒症の防止のため体重を抑制するケースや、医療技術の向上で未熟児等が増加するなど総合的な要因が関係しているのでは」と分析している。
今回は前回に続き、喫煙と身長、体重の関係について調査。全国から抽出した1万21人の乳幼児の母親のうち、「喫煙している」と答えたのは1005人で前回調査より4.4ポイント増えて10.0%で、たばこを吸う妊婦が増えている実態が明らかになった。
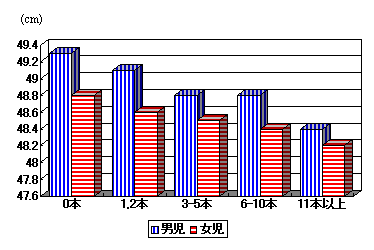
妊婦がたばこを吸う本数(1日当たり)と出生児の身長
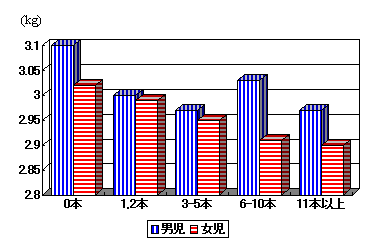
妊婦がたばこを吸う本数(1日当たり)と出生児の体重
喫煙本数別にみると、たばこを吸っていない母親から生まれた女児の平均体重が3.02㌔だったのに対し、母親がたばこを吸うケースでは、1日1、2本吸っていると2.99㌔、3〜5本では2.95㌔、6〜10本では2.91㌔、11本以上では2.90㌔だった。
身長もたばこを吸っていない母親から生まれた女児が48.8㌢だったのに対し、母親がたばこを吸っていると、48.2〜48.6㌢で、身長、体重とも喫煙本数に応じて低下する傾向があった。
男児でも母親がたばこを吸っていない場合、平均体重が3.1㌔だったのに対し、母親がたばこを吸っていると、3.03〜2.97㌔。平均身長もたばこを吸っていない場合は49.3㌢だったのに対し、たばこを吸っていると49.1〜48.4㌢で、女児と同様の傾向があった。
母親の年代別の喫煙率では、15〜19歳が34.2%で、20〜24歳が18.9%で、若い世代の妊婦ほど、たばこを吸うケースが多かった。
調査では初めて飲酒との関係も調査。飲酒している妊婦は18.1%で年齢とともに飲酒率が増加する傾向があったが、生まれてくる子供の体重や身長に対する影響は見られなかった。
